首都大学東京・宮城大学・デジタルハリウッド大学WS
三年生・四年生向けの課題です。まだ「素案」なので変わっていく可能性がありますが、とりあえずアップ。twitter、Google Earth、Second Lifeとてんこもり。 Google docsでも観られます 。 出題者:渡邉英徳・…
「こたつ問題」 on Stickam + Twitter
昨日 こんなイベント が建築会館で催されたので、twitter上で参加しました。 石川初さん に言及いただいてます。ありがとうございます。 当日のようす(取り急ぎ前半部分だそうです)が 配信されています 。 「こたつ問題」については 検索…
卒業制作/研究の進捗報告
週報 にあるとおり、昨日のスタジオゼミは卒業制作/研究の進捗報告会でした。wtnvスタジオでは9月より、隔週で各人の進捗状況を報告しあう会を持っています。 各々はブログで進捗報告を行っています。以下にそれぞれの報告に対するコメントやアドバ…
週報20090925
こんにちは、今週週報担当・倉谷です。 早いものでもうすぐ9月もおわりです。つまり夏休みが終わります。 この週報を書くのももう4度目になります。本当にはやいものです。 9月最後のミーティングは卒研の進捗状況をみんなの前で報告・アドバイスして…
ツバル・ビジュアライゼーション・プロジェクト公式サイト
ツバル・ビジュアライゼーション・プロジェクトの 公式サイトをオープン しました。 http://tv.mapping.jp/ 現時点では英語版のみ。また、レイアウトはbloggerのものを流用している仮版で、10月中旬に正式版が…
週報20090918
こんにちは、今週担当の河原です。 さていきなりですが、今週は各人の都合が合わず、スタジオミーティングは行われませんでした。 ただでさえ夏休み、そんなわけであまり書くことがなかったりします。 ただ、卒業制作に向けての活動は、みんな着々と進ん…
デジタルコンテンツエクスポ/ASIAGRAPH 2009
10/22-25に日本科学未来館で開催されるDigital Contents Expo 2009のサイトに「 ツバル・ビジュアライゼーション・プロジェクト 」の展示について 公式に告知が出ました 。なお首都大システムデザイン学部からは 串…
「ツバルマッピング」アップデート
現在、公開中の「 ツバルマッピング 」のコンテンツをアップデートしました。 Placemarkの高度調整を行い、研究生の 渡邊裕一君 謹製の Photo Overlay 変換サーバプログラムを活用することで、よりダイナミックに閲覧すること…
ツバルプロジェクト展示@ASIAGRAPH 2009
本日、採択通知がぶじ届き「 Tuvalu Visualization Project 」の ASIAGRAPH 2009 in Tokyo ARTECH(ART WORKS AND TECHNOLOGIES EXHIBITS)での展示が決…
週報20090904
こんにちは。今週週報担当の高田です。 まず始めに、今回はとてもいいニュースがあります。 倉谷さんが「せんだいデザインウィーク2009」のイメージシンボルキャラクターコンペで優秀賞を獲得しました! 詳細はこちら。 http://www.sd…
YouTube「HD特集」にツバルムービー掲載
YouTubeの HD動画特集 に「 Tuvalu on Photosynth 」が掲載されています。 サムネールのなかに「 Tuvalu on Photosynth 」が混じっています。みつけてみてください。YouTube…
Translate
Featured Post
Popular Posts

高分解能SAR衛星画像で見るウクライナ・マリウポリの被害

光文社新書『戦中写真が伝える 動物たちがみた戦争』刊行のお知らせ
【修論】kaleidomap: 地図をコラージュする地図表現の研究

【レポート】トルコ地震デジタルアーカイブ支援ワークショップ

東京都美術館『越境する心と芸術』展にAI短編映画作品を出品中

「押韻」の歴史的変遷と現代における「ライミング」活用の架橋

バレーボールの練習改善のためのプレー記録の視覚化

GPTsで小説生成ツールを作成しました

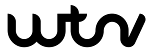
.jpg)



