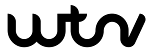東京大学大学院情報学環・文化人間情報コースの修士2年生ハオです。
2024年5月26日、NPO法人Piece of Syria(ピースオブシリア)と協力して、JICA地球ひろばで平和のかけらのワークショップを開催しました。
【ワークショップ概要】
今回のワークショップは、Piece of Syriaによるシリアの紹介、平和のかけらワークショップ、作品鑑賞の三部構成でした。参加者は親子と大人の二つのタイプに分かれて作業を行ないました。
【ワークショップの流れ】
01.Piece of Syriaの代表、中野さんによるシリアの生活・文化・近況の紹介
中野さんは自身の経験をもとに、シリアの生活を様々に紹介してくださいました。「怖い、危ない」というイメージとは異なり、喉が渇いたら地元の人がお茶やご飯をくれる、一緒に食事をしたら泊まるまで誘うなど、友好的な人々が住んでいる国だと認識できました。
 |
| 上記の問題の正解は③ |
02.ハオによる平和のかけらについての紹介
「平和とは何ですか?」というシンプルな質問から始め、その後、過去の平和のかけらワークショップで子供たちがどのようにこの質問に答えたかを紹介しました。
 |
| 平和とは「家族との旅行」 |
03.平和のかけらワークショップ
今回はウクライナ、シリア、ガザの写真を使用し、写真の背景、物、人を選び、具体的な形から抽象化した「ピース」を組み合わせて新しい平和のストーリーを作ります。
【平和のかけらワークショップのプロセス】
- 自己紹介、活動参加の理由、もらった写真の感想、ワーク1(この場面の問題・課題は何か?人々はどんなことを思っているだろうか?)についてシェアする(10分)
- 前のワークショップでの子供の絵を観察し、気づいたことをグループ内で共有する(12分)
- ワーク2(Piecesを組み合わせて「平和な世界はどんなものか」を考える)で、自分の作品を作る(25分)
- グループ内で作品発表(5分)
- ワーク3(ワーク1とワーク2を比較し、違いとその理由を考える。どのようにすれば平和なシーンを実現できるか、自分にできることを考えて書く)について考える(10分)
- 全体発表(子供たちによる)(10分)
 |
| 「木に引っかかった服を取る場面を考えたら、めんどくさいのが平和だと思った。」 |
 |
「家族と一緒にキャンプに行くのが平和だと思っています。」 |
この作品では、家族と一緒にキャンプに行く場面が描かれています。子供の作者は、キャラクターの4人を自分の家族一人一人に対応させ、服の色も合わせて描きました。「テント」のピースは戦争中は学校の一時的な場所ですが、平和な時代ではワクワクする遊び場になっています。
【参加者たちからもたった感想(部分)】
“Before&Afterで実際にどうすればこうなれるかと考える。実践的なワークショップで、絵というアプローチだったので、子供にもとっつきやすくてとても良かった。”“全国各地でやってほしいです。”“いろいろやっていたら、なんだか「平和のかけら」があつまったかんじがした。”
“平和と戦争というと、ヘビーな雰囲気になると想像をしたが、終始笑顔も絶えず、最後まで楽しく学べました。”
・「子供の視点から学ぶ」
今回は親子と大人が混ざる形で参加し、「子供の視点から平和を考える」というテーマでワークショップを企画しました。このように、大人が子供から「今の生活の中で何が平和か」、また「子供がどんな平和な未来を望んでいるのか」について考える機会となりました。
・「コミュニケーションの中で生み出す平和」
学校以外の場所でワークショップを開催することで、初めて会う人々が一つの問題について考え、議論し、互いの作品を見ることで「こんなにいろいろな発想が存在するんだ」ということを認識し、認めること自体が平和のアクションだと考えています。
・「平和とは何ですかー戦争の対立面以外の平和」
戦争についてはメディアの報道でなんとなくイメージがつきますが、「平和とは何ですか」について考える機会はますます少なくなっています。平和の定義は一人一人の心の中に存在しています。
子供の作品を振り返って考えると、日常生活を描いたシーンもあり、まだ実現していない未来の平和についての想像もたくさんあります。平和は必ずしも戦争の対立面だけではなく、戦争が起きていない国の中でも貧困や暴力、精神的な不安の中で生活している人々もいます。「WELL-BEING」という広い範囲で平和を定義するなら、平和な生活を実現するためには、世界のどこにおいても努力が必要と考えます。